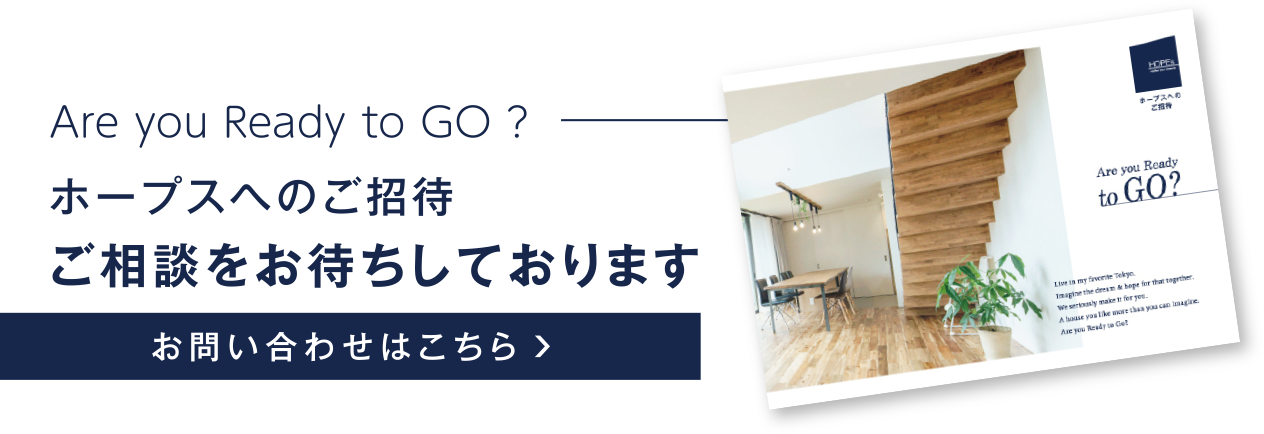カテゴリ:併用住宅のワークス
【賃貸併用住宅】 賃貸に向いている立地に家を建てる方にメリットのある土地活用方法です。また住宅ローンを使って建てられるので、アパートの家賃収入を住宅ローンの返済に充てる事が出来ます。固定資産税や相続税の税務対策になります。 【店舗併用】 お店として魅力的な外観に、印象的なファサードを意識した実例です。店舗併用住宅では住居と店舗という異なる環境を上手く機能させています。店舗でも自分の理想の生活を追求する事は変わりません。
【 併用住宅 】
賃貸住宅は、不動産賃貸経営を目的に建築する住宅、戸建て住宅の一部に賃貸住宅として建築する住宅は、賃貸併用住宅です。
賃貸住宅
賃貸物件は、外観デザイン、建物の雰囲気、内部の間取りや住宅設備機器のグレード、日当たりや風通し、駅から利便性、周辺の環境などによって、入居率が変わります。多少駅から遠くても、雰囲気が良く、暮らしやすい物件であれば、入居率を高められます。
入居者のターゲットを絞って、「デザイン性の高い賃貸住宅にする」「女性の一人暮らしでも安心して暮らせる対策を施す」「思わず住んでみたくなるような外観と間取りの賃貸住宅にする」などの工夫によって、人気の高い賃貸住宅を建てることが、空き室のない賃貸経営に繋がります。
賃貸併用住宅に設計プラン
1階を住居、2階以上を賃貸、または、3階を住居、下の階を賃貸というように、階ごとに住居部分と、賃貸部分を分けるプランと、2軒の家並べたようなを縦割りのプランが考えられます。
駅の近くであれば、単身者用の賃貸住宅の需要が多く、駅から遠くても家族で暮らせる広さの賃貸住宅には、子育て中の家族からの需要が見込まれます。
また、独立した子供が結婚したら同居する予定であれば、その時期が来るまで賃貸住宅として活用し、子供夫婦が戻ってきたときには二世帯住宅にするという考え方もあります。
賃貸併用住宅のメリットとリスク
賃貸併用住宅には、税金面や老後の生活などに対して、プラスになることがある一方、家賃が見込めなくなるリスクもあります。
ローンを家賃収入で返済
建て替えや新築を検討しているが、住宅ローンの負担を考えると、躊躇してしまうというような場合、賃貸併用住宅にして、家賃収入でローンを返済するという選択肢があります。
税金対策 家賃収入から控除される項目
固定資産税
所有している不動産は、市町村が課税する地方税が発生します。固定資産税の税額は「固定資産税課税標準額の1.4%ですが、住宅用地には、軽減措置があります。
賃貸住宅では、一戸につき200㎡までの敷地は、小規模住宅用地として扱われます。小規模住宅用地は、小規模宅地の特例によって、固定資産税は6分の1にされ、一戸につき200㎡を超える土地には、評価額の3分の1に軽減されます。
都市計画税
都市計画事業や土地区画整理事業を推進する費用を集めるため、市町村が条例で定めた区域内に、存在する土地や建物の所有者に対して課している地方税です。
小規模住宅用地は、軽減措置によって、都市計画税が、3分の1に軽減されます。また、建物に対しては1戸あたりの床面積が50m2(賃貸部分は40m2)以上280m2以下の建物で、120㎡までの居住部分に対して、3年間は固定資産税が2分の1に軽減されます。建物が、3階建て以上で、準耐火構造、または耐火構造であれば、軽減される期間が5年間に延長されます。
不動産取得税
戸建て住宅を取得した場合、建物に対して課せられる税金が不動産所得税です。条件を満たしている住宅は、その中から1,200万円が控除されますが、賃貸併用住宅の場合はそれぞれの賃貸住宅に対して、1,200万円が控除されます。
減価償却費
減価償却とは、資産を使用できる期間で分割して計上していく方法です。確定申告の際に、賃貸併用住宅の建築にかかった費用の賃貸部分に関して、原価償却をすることができます。
住宅ローンの利息
確定申告の際に、月々支払う住宅ローンの利息のうち、賃貸分の割合は、必要経費として算入できます。
賃貸併用住宅のリスク
賃貸併用住宅には、税金が軽減される、家賃収入で住宅ローンを賄える、老後に家賃収入を得られるといった魅力がありますが、空き部屋状態が続くなどのリスクもあります。
次に店舗併用住宅についてです。
「住居と繋がっているお店を持ちたい」
「隠れ家的なレストランを建てたい」
というような夢を叶える店舗や店舗併用住宅を建築する際には、一般的な戸建て宅とは異なる条件があります。
店舗・店舗併用住宅と用途地域
都市計画で定められた用途地域の中には、店舗や店舗併用住宅は建てられない、建てられるが床面積の制限がある地域があります。
第一種低層住居専用地域
敷地にゆとりを持った1~2階建ての戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街です。それぞれの住宅に住む人の住環境を保護するために、高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離などが定められています。
第一種低層住居専用地域で建築できる用途建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどです。
店舗の建築は認められていませんが、店舗併用住宅であれば、制限内で建てられます。
第一種低層住居専用地域で店舗併用住宅にかけられる制限
- 非住宅部分の床面積が、50㎡以下、建築物の延べ面積の2分の1未満のもの
- 住宅部分と非住宅部分が構造的にも機能的にも一体となっていて、用途的に分離し難いもの…店舗部分から住宅、住宅から店舗への移動の手段が、家の中にあること、店舗と住宅を仕切る部分に開閉できる開口部が設けられていること
第一種低層住居専用地域で非住宅部分にかけられる用途制限
近隣住民の日常生活に必要な施設等の兼用住宅と認められる業種であること
第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅
- 事務所
- 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
- 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋
- 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
- 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域よりは緩やかではありますが、制限があります。
この地域では、店舗併用住宅に加えて、制限内で店舗も建てられます。
第二種低層住居専用地域内に建築することができる店舗
- 2階以下の店舗
- 日用品販売店舗
- 喫茶店
- 理髪店
- 建具屋等のサービス業用店舗
第一種住居地域
戸建て住宅、マンション、用途際限内の店舗の建築が認められている地域です。
床面積が3,000㎡以下の店舗が建築できます。
3,000㎡以下であっても、カラオケボックス、パチンコ店などは建築できません。
第二種住居地域
床面積が10,000㎡以下の店舗が建築できます。
スポーツ施設は認められますが、カラオケボックス、パチンコ店などは建築できません。
店舗併用住宅と住宅ローン
店舗併用住宅の場合、基本的には、居住部分だけが住宅ローン控除の対象です。
店舗、または店舗併用住宅の店舗部分は、事業資金としての融資の対象です。
店舗併用住宅で住宅ローン控除を受けるための条件
- 住宅を取得した日から6ヶ月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日まで住み続けていること
- 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
- 返済期間が10年以上であること
- 合計の床面積が50m2以上であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
店舗部分の月々の返済分は、確定申告の際に、減価償却費として、経費に算入できます。